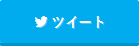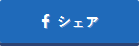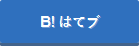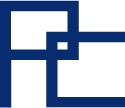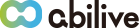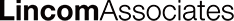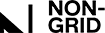【第362回】WEB集客最前線(観光インフレ時代に求められるWEB集客の視点) 2025/10/22|コラム
【第362回】週刊観光経済新聞掲載の、弊社取締役本部長 小林義道によるWEBマーケティング インターネット徹底集客の記事のご紹介です。
今回のテーマは、WEB集客最前線(観光インフレ時代に求められるWEB集客の視点)について。
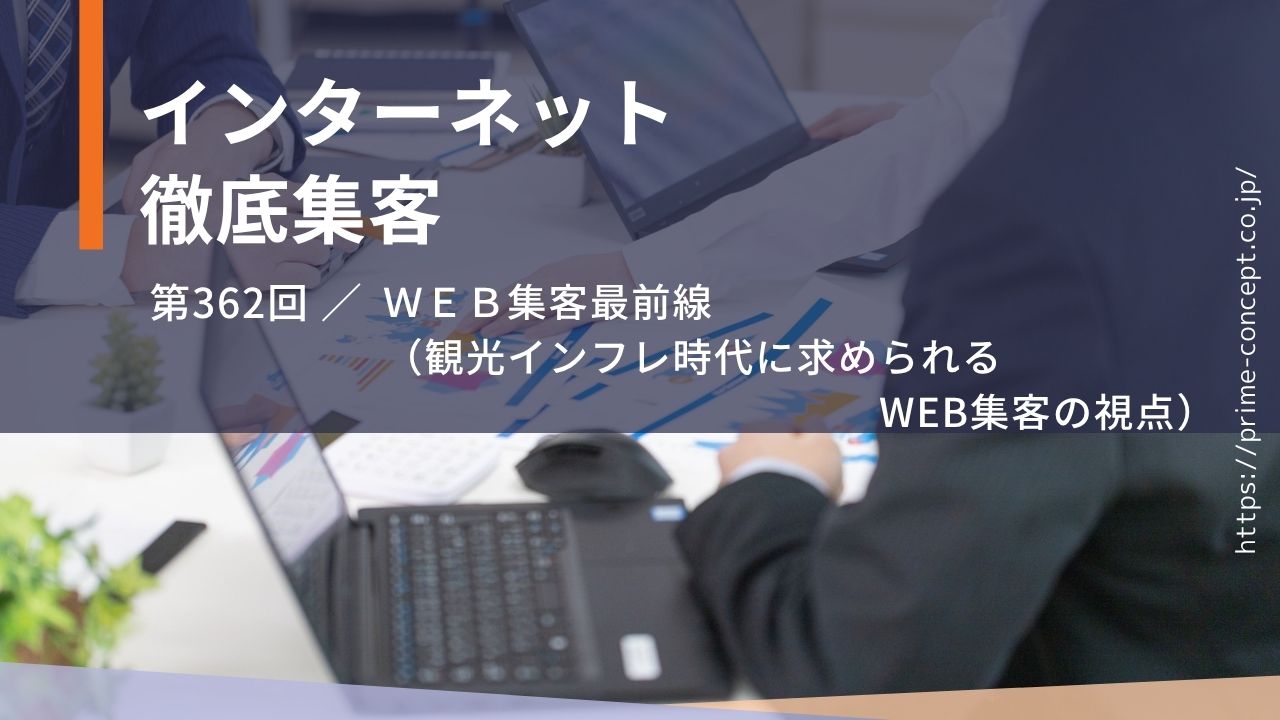
旅行が「割高な特別支出」として慎重に判断される傾向が強まっている
UNツーリズム(国連世界観光機構)の報告によれば、2025年前半(1~6月)の国際旅行者数は前年同期比約5%増の6億9,000万人に達したと見られる。
その中で日本は+21%と高い伸びを示した国の一つであり、観光収入も18%増と報じられている。インバウンド市場は拡大局面を維持し、国際的な観光需要の波は確実に戻りつつある。
一方で、「観光インフレ」は依然として高止まりしている。観光関連費用の上昇率は2024年の8.0%から2025年には6.8%へと緩和する見通しだが、2019年の約3%前後と比べると依然として高い。世界全体の平均的な消費インフレ率(約4%台)を上回る状況が続き、生活必需品以上に旅行関連費用の上昇が顕著だ。そのため、旅行が「割高な特別支出」として慎重に判断される傾向が強まっている。
近距離・短期間の旅行が主流になってきている
こうした環境下で、国内の旅行者行動にも変化が見える。
JTB「2025年夏休み旅行動向」によれば、総旅行者数は約7,464万人(前年比0.8%増)、旅行消費額は4兆円を超える見込みと堅調だが、旅行日数では「1泊2日」が最多(36.5%)で、近距離・短期間の旅行が主流である。
観光庁の調査でも「費用負担」「休暇取得の難しさ」が旅行を控える理由として上位に挙がり、旅行者の心理には「コスト」「時間」「距離」の三つの制約が色濃く影を落としている。
「納得価値」の提示
この「観光インフレ時代」において、WEB集客で求められるのは価格訴求ではなく「納得価値」の提示である。
料金に対し、体験や特典、安心感など“金額の理由”を明示し、顧客の心理的満足を支えることが重要だ。具体的には、宿泊後の満足度データや口コミを活用し、「なぜこの価格で選ばれているのか」を可視化する取り組みが有効である。
さらに、地域連携型プランやジオターゲティング広告を活用した近場需要の開拓、SNSや口コミによる共感型の発信も欠かせない。UGC(利用者投稿)はAI検索にも反映され、信頼性と推奨力を高める新たな資産となるだけでなく、宿自身のブランド文脈を形成する重要な要素となりつつある。
観光市場は量的に回復しつつあるが、消費者の価値判断はより繊細で現実的になっている。
いまこそ宿泊業界は、価格を下げるのではなく、体験の質と意味をどう伝えるかに力を注ぐべきだ。WEB集客は、その価値を可視化し、共感を生み出す最前線である。
(株式会社プライムコンセプト 小林義道)
人気の記事
-

2026.02.04 スタッフブログ
【保存版・2026年1月 更新】宿泊予約サイト(OTA)手数料一覧表
こちらは、OTAにおけるマーケティングや煩雑で面倒なプラン入力を一括管理で代行する「WEB集客サポートサービス」のスタッフが、宿泊施設様が気になっている情報や豆知識な...
-

2025.12.26 セミナー情報
【1/21開催】プライムコンセプトWebセミナー2026 選ばれる旅館のプラン設計~価格競争に陥らないための収益改善法~
無料セミナーのご案内です。 セミナーは事前お申し込み制、参加費無料です。 ▼▼ウェビナー参加申し込みはこちら▼▼ https://zoom.us/webinar/register/WN_D-k3YAufQCuuR...
-
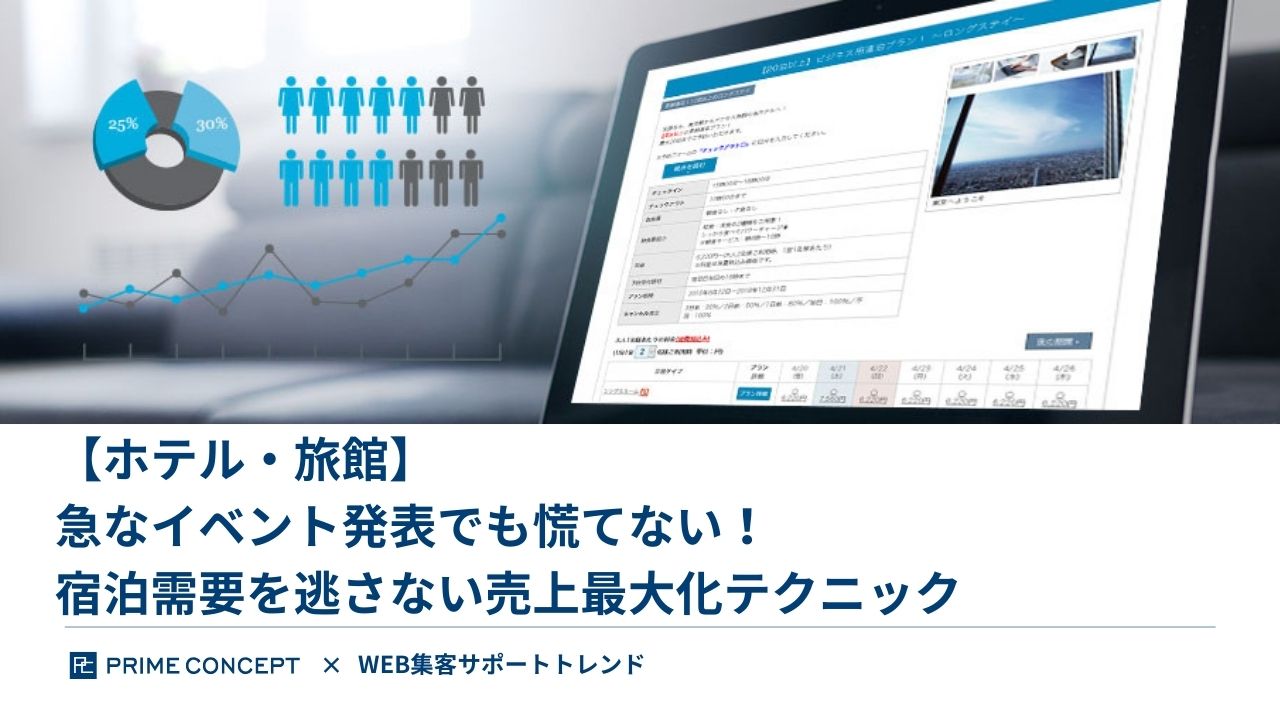
2025.12.11 スタッフブログ
【ホテル・旅館】急なイベント発表でも慌てない!宿泊需要を逃さない売上最大化テクニック
大型コンサートや人気イベントの開催発表後、ホテルがたった数時間で満室に。 そんなニュースが最近話題となりました。 コンサートや大型イベント開催時は、宿泊需要が一...
-
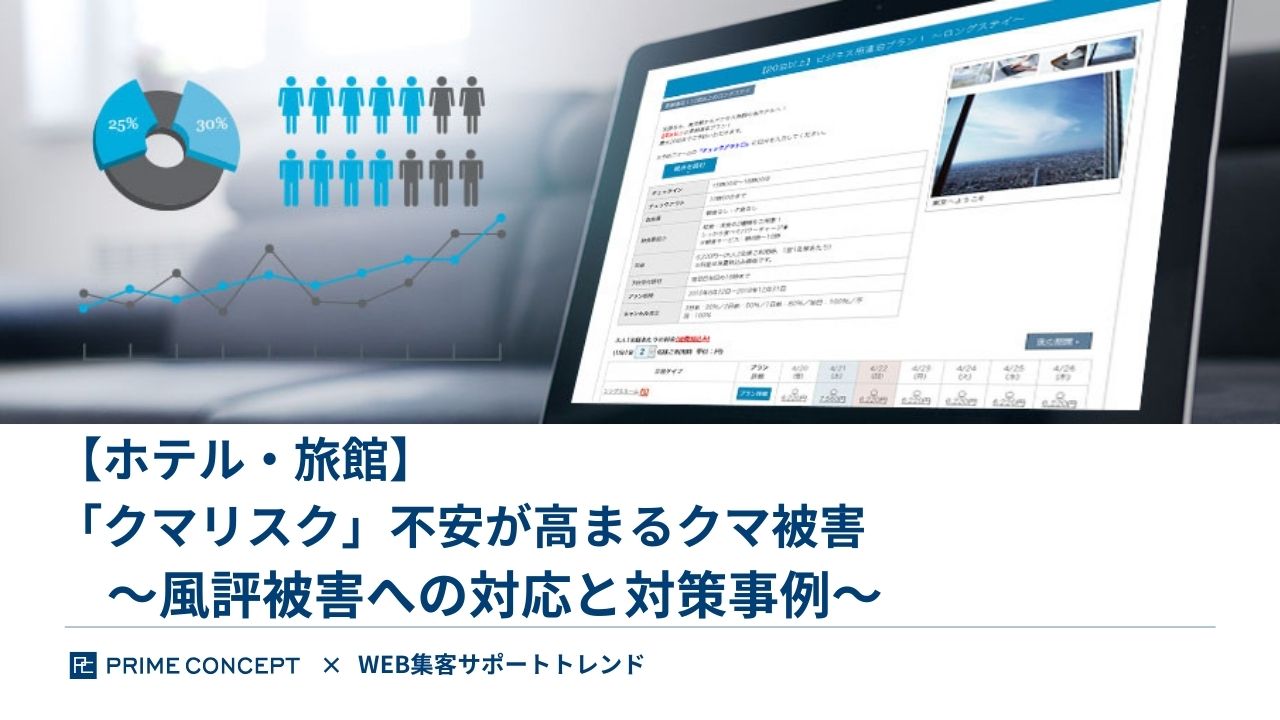
2025.12.25 スタッフブログ
【ホテル・旅館】「クマリスク」不安が高まるクマ被害~風評被害への対応と対策事例~
こちらは、OTAにおけるマーケティングや煩雑で面倒なプラン入力を一括管理で代行する「WEB集客サポートサービス」のスタッフが、宿泊施設様が気になっている情報や豆知識な...
-
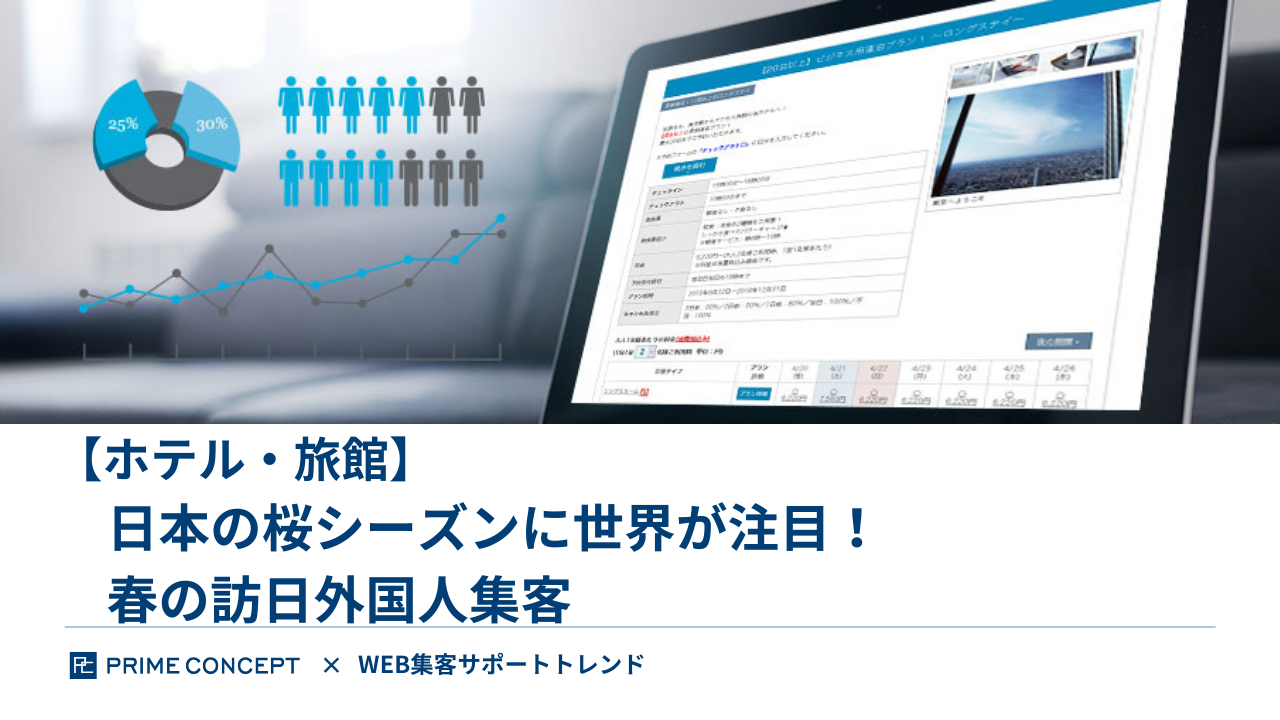
2025.12.18 スタッフブログ
【ホテル・旅館】日本の桜シーズンに世界が注目!春の訪日外国人集客
こちらは、OTAにおけるマーケティングや煩雑で面倒なプラン入力を一括管理で代行する「WEB集客サポートサービス」のスタッフが、宿泊施設様が気になっている情報や豆知識な...